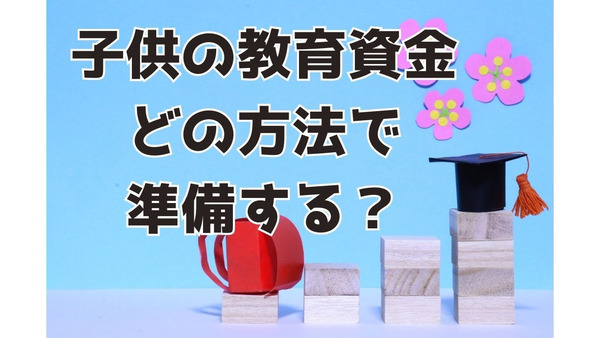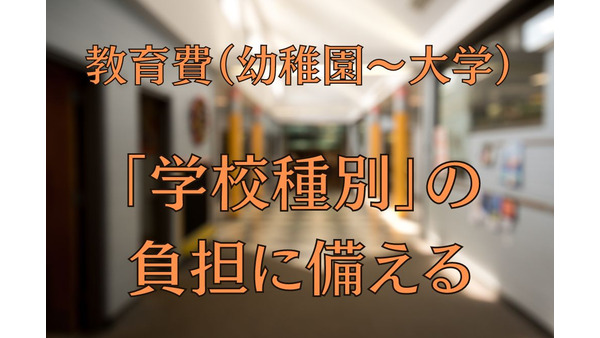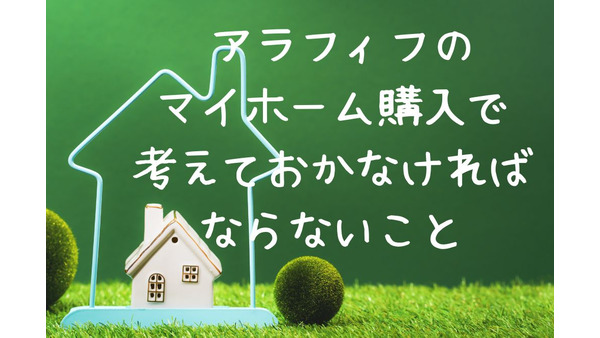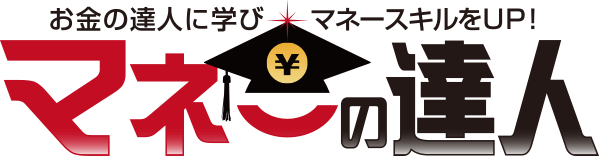人生の3大支出のひとつである「子どもの教育費」、試算するだけで頭が痛くなります。
教育資金はどうやって貯めていますか。
・ 定期預金
・ ジュニアNISA
しかし、ジュニアNISAは不人気すぎて2023年に廃止が決定しました。
そして廃止決定により、じわじわと資産運用好きの間で人気が増しています。

目次
ジュニアNISA最大のデメリット「払い出し制限」がなくなる期待
2020年の税制改正大綱が発表され、その中でジュニアNISAについて以下の決定がなされました。
未成年者口座開設可能期間は延長せずに終了することとし、その終了にあわせ、令和6年1月1日以後は、課税未成年者口座及び未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払い出すことができることとする。(引用元:財務省)
簡単に言うと「ジュニアNISAは2023年で廃止され、2024年以降はジュニアNISAで運用しているお金は自由に引き出せるようにします」ということです。
そもそもジュニアNISAが不人気だった最大の理由は、「子供が18歳になるまで払い出しできない」という使い勝手の悪さです。
これが撤廃されれば、利用価値は大きく上がります。
例えば、2020年からジュニアNISAで投資を開始した場合
・ 最長で子どもが20歳になるまで
非課税で運用でき、2024年以降は運用商品を売却して引き出せるということになります。
投資で利益が出た場合、本来は所得税や住民税などで合計20.315%が課税されます。
1万円利益が出たら約2,000円が税金で取られるので、これが非課税になるのは大きいです。
長期投資を非課税でできるメリットを享受でき、利便性も上がるため、子どもがまだ幼い家庭は特に有利な制度になります。
※2020年9月18日現在、大綱で示されただけでまだ法改正はされていません。
学資保険と預金では学費の上昇率に追いつけない

投資に前向きな家庭が増えている背景には、超低金利が続いて預金や学資保険では値上がりが期待できないことがあります。
私立大学の授業料が徐々に上がっていることは有名ですが、2018年頃から国立大学の授業料も大学間で差が出てきています。
国立大学の授業料は一律で基準額が決まっているものの、各大学の判断で最大20%までの増額が認められています(*1)。
現在の基準額は53万5,800円と、2005年からずっと変わっていませんが、2018年に東京工業大学が9万9,600円の値上げしたことを皮切りに徐々に値上げに踏み切る大学が増えています(*2)。
この流れは今後も続くと見られ、預金や学資保険でこの値上げの波に追随するのは困難と言えるでしょう。
参照:*1国立大学等の授業料その他費用に関する省令 第十条より
参照:*2日経経済新聞2018/9/14
長期投資の力は絶大
もし子供が大きくなるまでの時間で長期投資をしたらどうなるのでしょう。
例えば、老舗のバランスファンドとして有名なセゾンバンガードバランスファンドの場合、2007年5月の設立時に投資をしていたら、今年の8月で+56.01%になっていました(*3)。
一方で、定期預金で0.3%の金利がついたとしても、13年間で+4%弱しか増えません。
学資保険の返礼率もだいたい似たようなものです。
もちろん投資商品にはリスクがあります。
このバランスファンドもリーマンショックで最大35%ほど値下がりしていますし、そこから元の値段に回復するまで5年弱掛かっています。
そのため投資期間が10年以下と短くなる場合は、学費をジュニアNISAで運用することはおすすめしません。
また、学資保険は保険料払込免除のような親の「もしも」に備える側面が大きいため、学資保険はやめてジュニアNISAを優先すべきとも思いません。
しかしお子さんがまだ幼く、教育費がかかる時期まで10年以上の時間があるのなら、使い勝手が改善することを見越してジュニアNISAでの長期投資を考えても良いのではないでしょうか。
参照:*3セゾン投信

投資を選択肢に入れてみませんか
ジュニアNISAの廃止に伴い、デメリットであった払い出し制限が撤廃されることが期待されています。
わが家では
・ 10年以内に使いそうな学費として定期預金
・ 10年以上使わない余剰資金だけジュニアNISA
とし、メインは学資保険と預金、サブでジュニアNISAと分けて使用しています。
今後も値上がりが続く可能性のある教育費用に、制度をうまく使って備えたいです。(執筆者:青井 千夏)