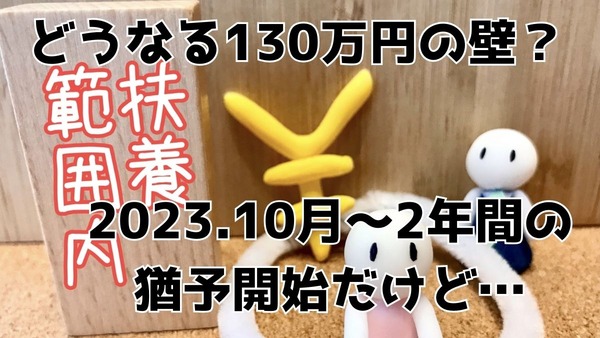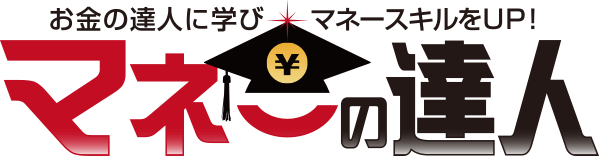そんなふうに夫婦は結婚生活に区切りをつけた瞬間に赤の他人に成り下がるのですが、それでも子の父、母であることは今後もずっと変わりません。
とはいえ、海外はともかく国内には共同親権という制度はないので、どちらか一方が親権を得て、もう一方は親権を失うのは確実。
親権者と「非」親権者との間に大きな壁が存在するのも事実です。
例えば、妻が子の親権を持った場合、非親権者である夫の役割は限定されます。
具体的には毎月の養育費、進学時の一時金、誕生日やクリスマスなどのプレゼントなど金銭面が中心です。
「現金を渡す」というわけではありませんが、扶養という形のサポートは意外と見落としがちです。
離婚後、子を父親、母親どちらの扶養に入れたら良いのでしょうか?
目次
「これから、娘の健康保険をどうしたらいいのでしょうか?」

そんなふうに頭を抱えるのは今回の相談者・岩瀬頼子さん。
夫:岩瀬純也(36歳)→会社員(年収500万円)
妻:岩瀬頼子(34歳)→パートタイマー(年収60万円) ☆今回の相談者です。
長女:岩瀬桜子(5歳)
結婚中、頼子さんの年金保険料、そして頼子さんと娘さんの健康保険料は、夫の給与から天引きされていましたが、離婚後、これらの保険料はどうなるのか…。
ただでさえ離婚後の生活に不安を抱えている中、頼子さんの心配は尽きませんでした。
大半の家庭で未成年の子供は「父親」の扶養に入っています。
しかし、「父親でなければならない」というルールがあるわけではなく、父親、母親どちらの扶養に入れることを自由に選ぶことができます。
夫婦の収入はほとんどの場合、夫>妻なので、夫の扶養に入れているのが現実です。
もちろん、夫婦が結婚している間は問題ありませんが、
二者択一の決断を迫られます。
「夫の(扶養の)ままって、本当に大丈夫なんですか?」

頼子さんが怪訝そうな顔をしますが、妻が親権を持ち、夫と子供は離れて暮らすのだから、妻の扶養に入れるしかないはず。
夫の扶養に入れるなんて不可能だと思い込んでいる人は多いです。
しかし、国税庁が公表しているタックスアンサーによると、
だという見解を示しています。
そのため、頼子さんの心配は杞憂に終わりました。
子を扶養に入れるメリットは、扶養手当の支給、扶養控除の適用等です。
一方のデメリットは、子供の健康保険の負担等です。
扶養手当は会社によって、健康保険の金額は年収によって異なります。
離婚後は103万円以上、稼げる見込みがあるかどうか
私は頼子さんに尋ねたのですが、妻の年収が103万円以上の場合、具体的に上記の金額を計算した上で、メリット>デメリットになれば、離婚のタイミングで夫から妻の扶養へ移すという手もあります。
一方、年収が103万円以下で扶養手当が支給されない場合、特にメリットはなく、子供の健康保険を負担するというデメリットだけが残るので、あまりお勧めできません。

頼子さんは答えますが、それなら夫の扶養に入れておいた方が得策でしょう。
夫の年収は500万円なので、会社から扶養手当が支給されるでしょうし、扶養控除が適用されれば税金は軽減されます。
娘さんの健康保険料を負担したとしても、メリット>デメリットなら手取が増えるのです。
夫の会社で計算してもらったところ、離婚に伴って頼子さんを扶養から抜き、娘さんを扶養に残した場合、夫の手取は毎月8,000円増えるようです。
最初のうち、夫はそんなふうに難色を示していたようですが、頼子さんは親権者なのだから夫の言い分も一理あります。
そして、娘さんは夫の会社の健康保険に入るので、娘さんの保険証は夫に交付されます。
そのため、保険証が切り替わるたびに、夫は頼子さんへ娘さんの保険証を渡さなければならず、夫としては手間が増えます。
しかし、夫としては頼子さんへ毎月5万円の養育費を支払いつつ、自分の生活(家賃、食費、水道光熱費など)を維持するのは大変なので、わずか8,000円でも手取りが増えることは貴重です。
そのため、途中まで意固地になっていた夫も最終的には観念し、「離婚しても子を扶養に入れ続ける」ことに承諾したのです。

まとめ
今回のように、非親権者である夫が子を扶養に入れることで、夫は手取が増え、妻は子の健康保険料を負担せずに済むので、双方にとって望ましいやり方です。
ほとんどの場合、何も考えず、扶養を夫から妻へ移してしまうのですが、一歩だけ立ち止まって「本当にそれでいいのかどうか」を一考していただければと思います。(執筆者:露木 幸彦)