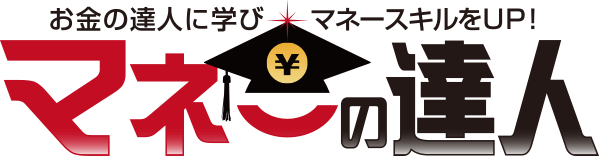目次
2020年の抱負はありますか
2020年、ついに東京オリンピックが開催される年になりました。
ねずみ年は十二支のはじめ、スタートの年でもあり、健康管理やダイエット、貯金や投資、趣味を楽しむなど新しいことをスタートしようと考えている方もいると思います。
弊社が開催するマネーセミナーには多くの女性が参加されます。
皆さん資産運用について学び、働きながら収入アップやキャリアアップを目指されています。
一方で、女性の社会進出が進んでいると言われていますが、世界と比べると日本で働く女性の収入や地位はまだまだ低いのが現状です。
今回は働く女性の現状や今後について考えていきたと思います。
女性の収入
平成30年分民間給与実態統計調査結果では、1年を通じて勤務した給与所得者の年間の平均給与は441万円であり、男女別にみると、
・ 男性545万円
・ 女性293万円
となっていました。

女性の収入が低いのは、正規雇用で長く働ける男性と比較して非正規雇用(アルバイトやパート等)で働くかたも多いことが要因の1つです。
平成30年の労働力調査(詳細集計)では、非正規の職員の内訳は以下となります。
男性31.6%、女性68.4%と非正規職員の約7割が女性であることが分ります。

女性はライフプラン(結婚や出産、介護等)の変化により、働けない期間があったり、正規雇用から非正規雇用へ雇用形態を変更したりするかたが多いのが現状です。
働き方改革が進められ、時短勤務やリモートワークなどを取り入れている企業も増えてきましたが、収入格差や非正規雇用の現状がすぐに変わるとは思えません。
また、収入が少ないということは、その分、納めている年金も少ないことを意味します。
将来、受け取れる年金額も少なくなりますので、足りない分は自ら準備(私的年金や預貯金)しなくてはいけません。
女性の地位
収入格差だけでなく、重要なポジション、例えば管理職や政治家も女性の割合が圧倒的に少ないのが日本です。
労働政策研究・研修機構がまとめた「日本の女性の活躍促進」に関する資料では女性管理職の割合は国際比較でみると依然として低いのが現状です。

また、政治の世界においても女性の割合が低い日本。
日本の女性議員が占める割合は10.2%で、調査の対象となった193か国のうち、165位となりました。
世界各国では女性議員の占める割合が増え続けていますが、日本は先進国の中でも最低水準にとどまっています。
男女雇用機会均等法(pdf)の施行から30年以上経った現在においても女性の収入格差や地位の向上が難しい現状がお分かりいただけるかと思います。
家事や育児、介護と仕事の両立など、より女性が働きやすく、そして長く働き続けることができる環境作り、企業や国の改革が今後も重要になってきます。
同一労働・同一賃金制度に向けて
2020年4月より施行される同一労働・同一賃金制度に向けて、企業では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指しています。
これまで、業務内容が同じでも、正社員、アルバイト、派遣などの雇用形態によって賃金が異なりました。
同一労働・同一賃金制度はその賃金格差を解消させるための制度です。
これにより、女性の働き方(働く時間や雇用形態など)が変化した場合でも安定した収入が得られるようになれば、賃金格差(収入格差)が少なくなるのではないでしょうか。
制度の導入にはさまざまな問題があるとは思いますが、不合理な格差をなくす1歩として期待したいところです。
自助努力の必要性

男女雇用機会均等法の施行から30年以上が経った現在でも、女性の収入や地位が低いことが分りました。
今年から同一労働・同一賃金制度が施行されますが、現状が制度の目的に達するまでに、どのくらいの時間がかかるかは分りません。
いつの時代でも、自助努力は必要です。
2020年はスタートの年なので、新たな自助努力をスタートしてみるのも良いのではないでしょうか。
(2) 私的年金を増やす
雇用形態にかかわらず、労働の内容により賃金が決められますので、これまで以上に知識やスキルアップは重要になってきます。
収入アップにつながるよう、新たな学びや資格取得なども必要です。
また、将来受け取れる年金を増やすために私的年金を準備することも重要です。
確定拠出年金や積立NISA、積立て保険などで私的年金を増やすのも良いのではないでしょうか。
これらの自助努力は、働いている皆さんの現在にも役立ちますが、将来にもつながる大切な努力です。
身についた知識やスキル、現役時代から積立てた私的年金は将来の皆さんの生活に役立ちます。(執筆者:藤井 亜也)