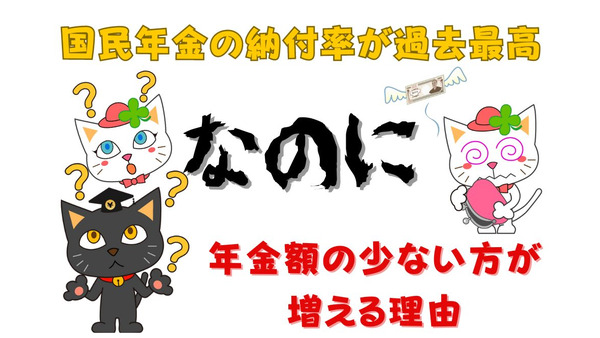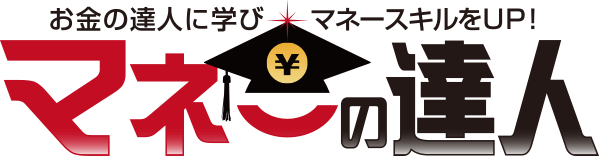既に加入者数が270万人を突破したiDeCoについて、「誰でも加入できる」制度と言われていますが、厳密には制度上、加入できない方も存在します。
今回は「iDeCoに加入するつもりでいたが加入できない」を回避するために、iDeCoに加入できない方について解説します。

目次
iDeCoの加入資格とは
年金制度には3つの区分があります。
自営業者等が加入する国民年金第1号被保険者、会社員等が加入する国民年金第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者です。
もちろん、いずれの被保険者区分の方であっても加入対象者ではあります。
どういう場合にiDeCoに加入できないのか?
第1号被保険者
障害基礎年金受給権者を除く保険料免除者、保険料納付猶予者は加入できません。
保険料免除者や保険料納付猶予者は多くの場合、失業等によって一時的に収入が少ない状況が続いている場合が考えられます。
他方、iDeCoは私的年金という枠組みの中で自己責任の元で掛金を拠出して将来の年金をより豊かにするための制度です。
よって、お互い、相反する状態となっており、加入者から除かれているということです。
ただし、障害基礎年金受給者については「法定免除」(障害等級1級または2級の受給者であれば国民年金保険料が全額免除される)必ずしも先の失業等の理由と合致しているとは限らないために除かれています。
第2号被保険者
企業年金に加入しており、マッチング拠出をしている場合は加入できません。
マッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に加え、加入者自身が掛金を(上乗せし)拠出することができる制度です。
加入者が拠出する掛金については全額所得控除の対象になるため、税制面でも恩恵があります。
言い換えると企業年金でマッチング拠出をしながらの状態でiDeCoは加入できないということです。
第3号被保険者
第1号被保険者と同様に20歳以上60歳未満という年齢条件がありますので、iDeCoの制度自体は65歳未満までの加入が可能となりましたが、第3号被保険者の場合はそもそも60歳到達によって資格喪失となりますので、60歳~65歳は加入することができません。
法改正によって加入可能となった方
旧来、iDeCoの加入可能年齢は60歳未満でしたが、65歳まで加入できるように改正されています。
ただし、60歳以降も加入できるのは第2号被保険者と任意加入被保険者となります。
任意加入被保険者とは国民年金の保険料納付済期間が40年に達していない方が(任意に)65歳までの間加入できる制度です。
ただし、65歳前に保険料納付済期間が40年に到達すると以後は任意加入被保険者として加入し続けることはできません(満額の老齢基礎年金を受給できるため)。
運用指図者
長期的にiDeCoを続けていくにあたり、一時的に掛金の拠出が難しくなることもあるでしょう。
その場合、運用指図者になるという選択肢があります。
運用指図者とは掛金の拠出は行わないものの、運用の指図のみを行う方を指します。
iDeCoは10年以上の加入がなければ60歳からの受給はできません。
10年に満たない場合は加入年数に応じて受給開始可能時期が段階的に先延ばしになってしまいます。
ただし、運用指図者としての期間は「通算加入者等期間」として、当該「10年」の期間にはカウントされますので、例えば加入者期間と運用指図者期間を合わせて10年あれば60歳から受給開始が可能です。
転職時などは再考しよう
iDeCoは多くの方が加入できるようになったことは間違いありませんが、制度上加入できない方も複数存在します。
また、拠出限度額も加入者資格ごとに上限が異なっていますので、特に転職時などは再考すべき機会と言えます。
また、今後のライフイベントを見越して、いつまで加入できるのかの見通しを立てておくことも重要です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)